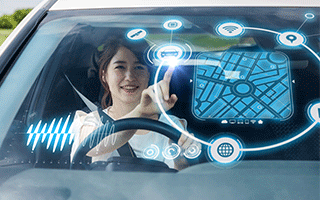ライドシェア、自動運転、人工知能がもたらす環境変化と適応方法
(※このコラムは、2016年11月のチームエルレポートに掲載されたものです。)
20年後、自動車保有台数は、3割減少する
自動運転、ライドシェアなど新たな技術や潮流により、「20年後、日本の自動車保有台数は、3割減り、完全自動運転の普及も始まる。」との予測がある。
また、今後20年で人工知能が5割、あるいは、9割の仕事を奪うとの予測もある。このように激しい環境変化への適応方法について考えてみましょう。
ライドシェア(相乗り)の需要が増大する
日本では、なじみが薄いが、欧米では、ライドシェアが急増している。
この現象は、「自家用車は、1日平均走行距離15km、時間40分(3%)しか稼働していないのに、本当に保有が必要なのか」との問題を提起している。
業界最大手のウーバーテクノロジーズは、2009年設立だが、2015年売上1.3兆円となり、企業価値はGMを超えている。
タクシー配車、自家用車による有償運送の仕組みを構築し、顧客と運転手の「相互評価」でトラブルを回避し、サービスを拡大している。
日本では、2014年8月、東京でタクシー配車サービスを開始。2015年2月、福岡市で「みんなのUber」を開始するが、国土交通省から「白タク行為に当たる」と指導が入り、サービスを中止した。
しかし、公共交通空白地は、白タク行為が特例で認められていることから、2016年5月、京丹後市丹後町で有償運送の「ささえ合い交通」を開始。地方での実績をテコに規制緩和を狙っている。
日本は、ぼったくりなどのタクシートラブルは少ないが、タクシーを呼ぶのに1時間以上かかる地域や時期があり、ライドシェアの需要はある。今後は、急増する高齢者や観光客の交通手段としても、ライドシェアの増大が予想される。
自動運転、宅配、遠隔医療で保有台数が減少する
20年後、完全自動運転車の普及が始まる。ドライバーが不要になれば、ライドシェアもタクシーも境界がなくなり、無人タクシーになる。
多くの乗用車が無人タクシーになれば、運賃も安くなる。スマホで自宅まで呼び出し、目的地で乗り捨てるので駐車料金も、駐車場を探す手間もかからない。
高齢者が運転に不安を感じつつも車を手放せないのは、買い物や通院などに不可欠だからだ。
しかし、食品や日用雑貨、衣料、書籍などでも宅配が普及してきている。
ドローンによる宅配が実現すれば、過疎地でも宅配が可能になる。
また、遠隔医療で通院も減る。外出の頻度が減れば、保有よりもライドシェアや無人タクシーに移行する。
自動車保有台数は、若者の車離れや少子高齢化により、10年後に1割減少する。さらに、宅配や遠隔医療の充実に加え、自動運転やライドシェア、無人タクシーの利用増大により、20年後に3割減少する。
人工知能が仕事を奪い、私たちの仕事が変わる
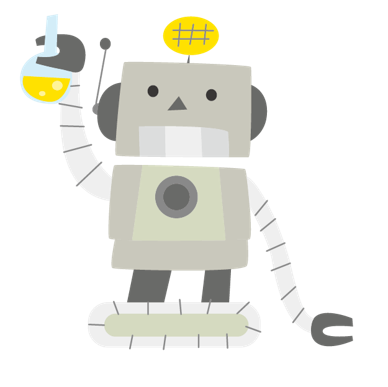
銀行は、人工知能が顧客に最適な金融商品を提案するようになり、ウェアラブル端末で振込もできるのでATMや支店も不要になり、銀行員も25万人から5,000人(2%)に減るとの話もある。
銀行ほど激しくはないが、人工知能は、今後20年で仕事の5割あるいは9割を奪うと言われている。単純労働だけでなく、SE、会計士、弁護士、医師、コンサルタント、セールスなどの知識労働も例外ではない。
つまり、私たちに求められる仕事が大きく変わる。では、何をすればよいのか。そのヒントが、書籍「ハイ・コンセプト 新しいことを考え出す人の時代」に示されている。
ハイ・コンセプトでハイ・タッチな6つの感性とは

1.機能だけでなく「デザイン」
機能だけでは不十分。外観が美しく、感情に訴えかけてくるものを創る。
2.議論よりは「物語」
情報が溢れた現在、議論だけでは不十分。
説得やコミュニケーションに肝心なのは、「相手を納得させる話ができる能力」である。
3.個別よりも「全体の調和」
知識労働も海外やオートメーションに奪われる。
「バラバラなものをつなぎ合わせて印象的で新しい全体観を築き上げる能力」が重要になる。
4.論理ではなく「共感」
情報が溢れる現在、論理だけでは成功しない。
成功する人は、「人間関係を築き、他人を思いやり、人を動かす能力」を持っている。
5.まじめだけでなく「遊び心」
笑い、快活さ、娯楽、ユーモアが健康や仕事にも恩恵をもたらす。まじめにならなければならない 時もあるが、深刻になりすぎるのは悪影響がある。仕事にも人生にも遊びが必要だ。
6.モノよりも「生きがい」
物質的に豊かな世界は、生活に苦しむことから解放され、
有意義な生きがい(目的、超越、精神の充足)を追求できるようになった。
ハイ・コンセプトの時代を実感する

人々は経済的豊かさよりも、生活の意義を重視するようになった。
その結果、品質、価格などの左脳的価値が相対的に低下し、デザインや物語、全体の調和、共感、遊び、生きがい等の右脳的価値が高まった。
実際、カーセンサーやGoo、アマゾンや楽天、ぐるなびや食べログなどのネット検索サイトを使い、品質や数量、価格で商品を絞り込み、最後は、総合評価、口コミ、画像を確認し、購入商品を選ぶ。
その際には、デザインや共感、物語、遊びが決め手になることが多い。
皆様も同様の消費行動をしていないだろうか。
インターネットにより、消費者の情報収集力が高まり、セールスも、話す力よりも、聴く力が重要になってきた。
商品説明や論理的な対話は、ペッパーのような対話型ロボットに奪われる。
その分、共感が必要な会話や雑談の重要性が高まってきた。
この領域は、人工知能には奪われない。
「全体の調和」も重要になってきた。残クレ(新車購入+残価保証+3年代替の魅力や楽しさ+メンテナンスパック)、委託販売(買取+直販代行+愛車心への共感)、長持ち車検(車検+予防整備+安全+トータルコスト抑制)などは、まさに全体の調和が新たな価値を創造している。
但し、啓発力が弱いと、その魅力がお客様に伝わらないから訓練が重要になる。
共感力、啓発力で人工知能の時代に適応する
人工知能に仕事が奪われると、商品やサービスの価格が安くなり、余暇も増えるので、消費者には良い話だ。
しかし、共感力や啓発力に乏しく、左脳思考偏重の人材は、仕事を失う厳しい時代になる。
この環境変化に適応するには、右脳思考を鍛え、共感力と啓発力に磨きをかけることが重要だ。
そうすれば、存在価値が高まり、楽しい時代になる。
仕事は、「全体の調和」による商品開発と啓発力で新たな価値を創造する。
人生は、生きがいを持ち、他人を思いやり、楽しく、美しく生きる。これは、まさに、人間性を高めることだ。
仕事も人生も試練を乗り越え、物語を紡ぐ。その要諦は、ポジティブ思考と行動力にある。
| (参考文献) ・週刊東洋経済6月25日号 ・Wedge7月号 ・世界大激変 次なる経済基調が定まった、 長谷川慶太郎(著)、東洋経済、2016年8月 ・ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出 す人の時代、ダニエル・ピンク(著)、 大前研一(訳)、三笠書房、2006年 |

常務取締役 關 友信 Seki Tomonobu
損害保険会社の営業社員から独立しプロ代理店を経営、その後、自動車販売店での企業を目指し、直営店に入社する。販売店の現場で買取査定や販売業務を経験し、直営店の店長やエリア統括マネージャーとして活躍する。2006年に愛車広場カーリンクのチェーン展開を開始したのと同時に、カーリンク基礎研修の開発に着手、カーリンクチェーンの研修チームを統括する。その後も直営店の出張査定センターのマネジメントやディーラーコンサルティングなど、幅広く様々な仕事を経験、2014年からはCaSSの会員制度を立ち上げ、会員向けのサービスや企画を開発。